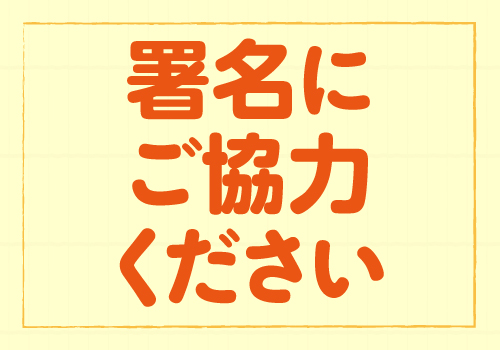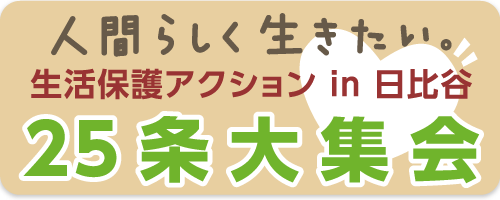ニュース
東京高裁(東京はっさく訴訟・さいたま訴訟)で連日の勝訴!高裁でも6勝4敗とリード広げる(判決全文・要旨・弁護団声明も掲載しています)
2025.3.31

2025年3月27日、東京高裁(はっさく訴訟)で勝訴!
22025年3月27日14時、東京高等裁判所第8民事部(三角比呂裁判長)は、東京都内の生活保護利用者27人が国と自治体を被告として提訴した裁判の控訴審において、訴えを認めた1審東京地裁判決を支持し、生活保護基準引下処分を違法として取り消す原告側勝訴判決を言い渡しました。
地裁段階において敗訴続きだった前半戦の流れを大きく変えた2022年6月24日の東京地裁判決(清水知恵子裁判長)の判断が東京高裁でも維持されたこと、従前の主張が維持できず主張を変遷させた国側の新主張をことごとく明快に排斥したことには大きな意味があります。
すなわち、本判決は、判断枠組みについては清水判決の骨格を維持しつつ(15~17頁)、「デフレ調整」について、一般世帯と保護受給世帯の消費構造の差からテレビ等の価格下落による物価下落の影響の程度は保護受給世帯においては相対的に小さいことに加え、平成22年ウエイトを用いたことによる下方バイアスの可能性等も考慮すると、-4.78%に匹敵する「生活扶助基準の水準の実質的な引上げ」があったと評価することには「相当な疑義がある」として、厚生労働大臣の判断は、統計等との客観的数値等との合理的関連性等を欠くと判示しました(43~47頁)。
また、清水判決同様に、引下げの保護受給世帯の生計維持への影響の重大性を認めるとともに(53~54頁)、激変緩和措置による影響緩和の程度は限定的で被保護者の日常生活にかかる期待的利益に対する配慮に欠けるとも判示しました(55頁)。
そして、変遷を重ねる国側の新主張については、①判断枠組みについて朝日訴訟基準によるべきとの主張(17~19頁)、老齢加算基準+朝日訴訟基準によるべきとの主張(20~21頁)、②老齢加算最判は老齢加算という既得権に関する判断との主張(19~20頁)、③司法審査にあたり参照できるのは現に用いられた統計等に限られるとの主張(21頁)、④デフレ調整の論拠について、「一般世帯との不均衡是正」であるとする主張(47~49頁)、夫婦子1人の低所得世帯の消費水準との比較によると下落率(11.6%、12.6%)が高くなりすぎたとする主張(50~51頁)などを、ことごとく明快に排斥したのです。

判決後の記者会見で、宇都宮健児弁護団長は、「最高裁の判断に向け、原告側の追い風になった」と手ごたえを語りました。
2025年3月28日、東京高裁(さいたま訴訟)でも連勝!
2025年3月28日14時、東京高等裁判所第16民事部(佐々木宗啓裁判長)は、埼玉県内の生活保護利用者が国及びさいたま市等を被告として提訴した裁判の控訴審において、訴えを認めた1審さいたま地裁判決と同様に生活保護基準引下処分を違法として取り消す原告側勝訴判決を言い渡しました。

1審さいたま地裁判決は「デフレ調整」の違法性は認めず、「ゆがみ調整」の2分の1処理の違法性のみを認めるという珍しい判断でしたが、本判決は、「ゆがみ調整」の2分の1処理の違法性を認めなかった一方で、「デフレ調整」の違法性を認めるという判断をしました。
本判決は、「デフレ調整」の各論点(生活扶助相当CPIを算出する際の統計資料、計算方法、算定の始期、ウエイトの参照時点等)については、厚生労働大臣の裁量権の範囲の逸脱、その濫用は認められないとしても、個々の裁量的判断を積み重ねた結果、一連の判断としてみれば、-4.78%の「下落率をそのまま一律にデフレ調整分の改定率としたその判断は、統計等の客観的数値等との合理的関連性又は専門的知見との整合性を欠くものといわざるを得ず、同判断には生活保護法が定める最低限度の生活の具体化に係る判断の過程に過誤、欠落があるものと認めるほかはない。」と判断しました。
本判決には、国家賠償請求を認めなかった点や、「デフレ調整」における個々の重大な問題を軽視する点に大きな問題はあります。 しかし、1審判決が採用しなかった老齢加算最高裁判決の規範(統計等の客観的数値等との合理的関連及び専門的知見との整合性)を採用した上で、総合評価とはいえ「デフレ調整」の違法性を明確に認めた点、「デフレ調整」の論拠等についての国側の変遷した主張を明快に排斥した点、そして、最高裁判決を控えたこの時期に東京高裁で連日の勝訴判決が得られた点において、大きな意義があります。

判決後の報告集会で、原告の男性は、「勝ててうれしい。亡くなった方もいるが天国で喜んでくれていると思う」と喜びを語りました。また、原告の女性は、「生活保護の水準は低すぎる。受給者の生活は健康的でも文化的でもなく両方を少しずつあきらめてきた」と保護基準引上げの必要性を語りました。
5月27日、いよいよ最高裁での弁論へ!
全国29地裁で提起された同種訴訟で、これまでに言い渡された40判決(地裁30、高裁10)のうち、原告側は25勝15敗(地裁19勝11敗、高裁6勝4敗)となりました。地裁段階同様、負けが先行した高裁での闘いも逆転勝訴が相次ぎリードを広げました。
今年に入ってからは原告側の6勝1敗で、最高裁での弁論・判決を目前に控えて原告側勝訴の流れは確定したといえます。
■いのちのとりで裁判・判決一覧表(PDF)
4月18日14時30分からは広島高裁、5月21日14時からは福岡高裁(熊本訴訟)、6月11日14時30分からは前橋地裁、6月25日13時30分からは名古屋高裁金沢支部(石川訴訟、富山訴訟)での判決が予定されており、引き続き帰趨が注目されます。

最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)は、3月26日、先行する大阪訴訟(高裁で逆転敗訴)と名古屋訴訟(高裁で逆転勝訴)について弁論期日を5月27日午後と指定しました。本年7月の宇賀裁判長の定年退官までに最高裁の統一判断が示されると思われます。
裁判所近くの日比谷公園では、桜の花が咲き誇り始めています。最高裁で勝訴判決を勝ちとるため、私たちは全力を尽くします。引き続きご注目とご支援をお願い致します。