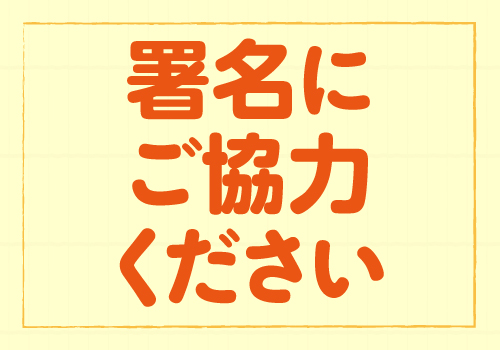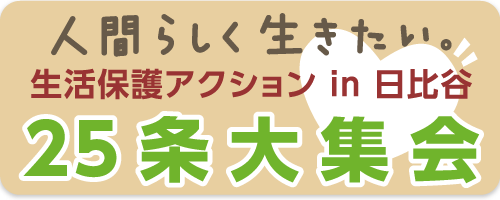ニュース
札幌高裁でも逆転勝訴!(判決全文・要旨・弁護団声明も掲載しています)
2025.3.24

2025年3月18日13時30分、札幌高等裁判所第3民事部(斉藤清文裁判長)は、新・人間裁判(生活保護基準引下処分取消請求札幌訴訟)控訴審において、控訴人らの請求を棄却した札幌地裁判決を取り消し、生活保護基準引下処分を取り消す逆転勝訴判決を言渡しました。
この裁判は、北海道内の生活保護利用者153名が、北海道及び各自治体を被告として、2013年から3回に分けて行われた生活保護基準の引下げの取消を求めた裁判です。2021年3月の札幌地裁判決は、不当にも原告の請求を棄却しましたが、105人の原告が控訴審に立ち上がりました。この4年間に14人の原告が亡くなってしまいましたが、95人の控訴人で控訴審判決を迎え、逆転勝訴判決を勝ち取りました(4人の控訴人については、訴訟を承継することも認められました)。
全国29地裁で提起された同種訴訟で、これまでに言い渡された38判決(地裁30、高裁8)のうち、原告側は23勝15敗(地裁19勝11敗、高裁4勝4敗)となりました。地裁段階同様、負けが先行した高裁での闘いも逆転勝訴が相次ぎこれで五分五分となりました。

裁判所には、300人近い原告と支援者が集まりました(原告は35人が集まりました)。90席余りの傍聴席は満員になり、傍聴できなかった200人以上の支援者は寒空の中待機しました。

本判決は、「デフレ調整」について、それを実施すること自体が合理性を欠くとはいえないとしつつも(35頁)、①物価考慮について生活保護基準部会等での「議論が熟していなかった」こと(20~21頁)、②最後の改定が行われた平成16年を算定の始期とすることにも一定の合理性があるのに20年を始期としたこと(22頁)、③平成22年ウエイトによる算定は下方バイアスが生じるパーシェ方式と同様の結果になること(21頁)、④社会保障生計調査に基づく算定では単身世帯-1.48%、複数世帯-2.12%にとどまるのに(原告弁護団の算定を採用)、消費構造が大きく異なる一般世帯についての家計調査に基づくウエイトを用いたこと(25頁)を指摘したうえで、「幅があり得る数値の中で、いずれも下落率が大きいほうの値を採用し、取り分け一般世帯と比較することによって下落率が大きくなる方向で算定」し、「過剰な下落率を定めた可能性がある」ことなどから、「生活扶助基準の改定に係る過程及び手続において、過誤、欠落の有無等の観点から、統計等の客観的な数値等との合理的関連性を欠く」として、厚生労働大臣の判断を違法としました(28~29頁)。
また、本判決は、生活扶助が、憲法25条の理念に基づいて生活保護法が定める各種の保護の中でも基礎的な生計に関わるもので(18頁)、「生存の糧となる」ものであることから、「これが不要に切り下げられた場合には要保護者の生活に著しい負担を与えることは明らかである」として(29頁)、要保護者が受ける被害の大きさにも言及しています。
さらに、本判決は、被控訴人が控訴審で行った2つの新たな主張(①朝日訴訟最高裁判決基準を採用し、裁量権の逸脱濫用をより狭く判断すべきである。②本件の改定は平成29年検証等で確認されており問題ない)について、いずれも明確に排斥しました(①31~32頁、②36~38頁)。

報告集会でも300人近い原告と支援者が会場に集まり、ネット配信でも35か所から参加があり、勝訴判決を喜びあいました。
報告集会には、新・人間裁判のキャラクターのニゴヤンも登場。ニゴヤンと一緒に勝訴判決を喜び合い、最高裁での勝訴に向けて闘うことの決意も固めました。
私たちは、被控訴人らが速やかに2013年引下げ前の生活保護基準に戻し、生活保護基準を引下げられた全ての生活保護利用者に対し真摯に謝罪することを求めるとともに、最高裁における完全勝利まで断固として闘い抜く決意です。