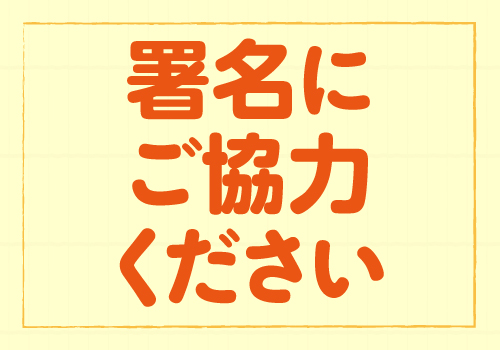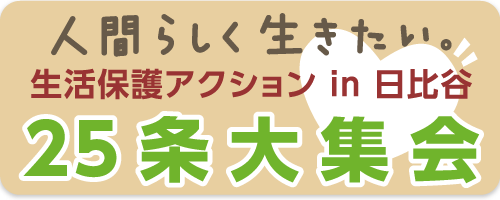ニュース
大阪高裁(京都訴訟)で逆転勝訴!(同日言い渡された福岡高裁(佐賀訴訟)判決もあわせて判決全文・要旨なども掲載しています)
2025.3.17
大阪高裁(京都訴訟)は逆転勝訴!

2025年3月13日午後2時、大阪高等裁判所民事第3部(佐藤哲治裁判長)は、京都市内の⽣活保護利⽤者32名が国及び京都市を被告として提訴した裁判の控訴審として、訴えを退けた1審京都地裁判決を取り消し、保護変更決定処分(⽣活保護基準引下げ)の取り消しを命じる逆転勝訴判決を言い渡しました。
全国29地裁で提起された同種訴訟では、国家賠償まで認めた名古屋⾼等裁判所を含め地裁、⾼裁で合計21件もの勝訴判決(地裁19件、⾼裁2件)が出されており、22件目(高裁では3件目)の勝訴判決です。

原告団、支援組織、弁護団に加えてテレビ局や新聞社など多くの報道関係者も注目する中、202号大法廷にはたくさんの方が詰めかけ、傍聴席も満席となりました。
判決では国家賠償請求こそ退けられましたが、1審京都地裁の恥ずべき「コピペ判決」から一新された判断が随所に光る、素晴らしいものでした。
本判決の特徴は第一に、厚生労働大臣の裁量判断の適否について、老齢加算最高裁判決が示した「主として最低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があるか否か等の観点から統計等との客観的数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等について審査する」との判断枠組みを採用しつつ、「(生活保護法8)条1項による委任の範囲を逸脱する」(9頁)、「厚生労働大臣は、保護基準を定めるに当たって同法8条2項所定の事項を遵守することを要するのであるから、厚生労働省に認められた裁量権は、立法府において憲法25条1項の理念を実現する法律を制定する際に立法府に認められる裁量権と同様であるということはでき(ない)」(23頁)等として、各条文の構造をしっかり示したことにあります。
その上で、保護受給世帯と一般世帯との間の消費構造には無視しえない相違があるとして、デフレ調整として生活扶助基準を4.78パーセント引き下げるとした厚生労働省の判断は判断過程における過誤があり、ゆがみ調整とデフレ調整は不可分一体のものとして、引き下げ全体が生活保護法3条、8条2項に違反し8条1項の委任の範囲を逸脱する違法なものだとしました(39~40頁)。
さらに本判決は、国の用いた物価指数それ自体が、「平成22 年という新しい時点を基準に価格⽐を⽤いて算出された平成20年の価格指数を基礎とする⽣活扶助相当CPI」を⽤いながら、他⽅で、「平成22 年という過去の時点を基準に価格⽐を⽤いて算出された平成23年の価格指数を基礎とする⽣活扶助相当CPI」を⽤いることは⼀貫性を⽋き、これらの⽣活扶助相当CPIを前提とする-4.78%という変化率は統計上の正確性が担保されていない」と厳しく断じ、この点からも違法であるとしました。
しかも本判決は、過去の国会質問や本件を含む各種訴訟で国がこれまで展開していた主張、そして今回の引き下げに携わった厚生労働省担当者の名古屋地裁での証言にも触れながら、国の新主張(ちゃぶ台返しその1、その2)をひとつ一つ否定し、「保護課において、本件扶助改定までに(ちゃぶ台返し1のための)計算をしていたと推認することはできないし、まして、その計算結果を厚生労働大臣が把握していたと認めることは困難というほかない」(32頁)、「(ちゃぶ台返し2の内容が厚生労働)大臣の判断過程に入っていたと認めることはできない」(同)として、事実認定のレベルで国の主張を完膚なきまでに否定しました。

判決後の記者会見・報告集会では、節約に心をすり減らしてきた様子(竹井登志郎さん)や大阪高裁で初めての勝訴で大阪事件・兵庫事件の借りを返せたことの安堵(森絹子さん)など、たいへんな思いで裁判を続けてきた原告・支援者から喜びの声が次々上がりました。
また、京都から始まった生存権裁判の提訴から数えて20年の節目に「京都新・生存権裁判」が勝利を迎えることの意義(尾藤廣喜弁護団長)も確認されました。
集会の中でも、提訴から今日までの間に勝訴判決を迎えることなく多くの仲間が亡くなったことが改めて確認されました。実に96パーセントの生活保護世帯を対象として行われたこの引き下げの被害救済には一刻の猶予もありません。
同日言渡しの福岡高裁(佐賀訴訟)判決は敗訴
大阪高裁(京都訴訟)判決が言い渡されたのと同じ2025年3月13日午後2時20分、福岡高裁第3民事部(久留島群一裁判長)は、佐賀訴訟の控訴審で原告側の控訴を棄却する原告側敗訴判決を言い渡しました。
判決は、判断枠組について、老齢加算訴訟最高裁判決が採用した判断過程審査を用いつつ、変遷した国側の主張を受け入れ、朝日訴訟最高裁判決等を参照し、判断過程の過誤、欠落が「重大なものであって、そのために現実の生活条件を無視して著しく低い保護基準を設定した」などの場合に裁量権の逸脱・濫用になるとしました。そして、生活保護が予算措置を伴う以上、財政事情を考慮せざるを得ないし、「納税者の理解は、必須」と、国側さえ主張していない価値判断を示して広い裁量権を許容しました。
かかる判断枠組のもと、①デフレ調整、②ゆがみ調整の2分の1処理、③デフレ調整及びゆがみ調整(2分の1処理)を併せて行ったことについては、原審の判断をほぼ踏襲し、いずれもその判断の手続及び過程につき、過誤、欠落は認められず、裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるとはいえないとしました。
さらに、①デフレ調整の根拠について変遷している国側の主張は「簡単には採用できない」し、生活扶助相当CPIの算出過程にも「相当の疑問はある」としながらも、「国家財政が危険水域と評される反面、生活保護事業費が増大し」、「切り下げを基礎づける状況に対応するかどうかの決断を迫られ」、「生活保護受給者に相当の受忍を求め、生活保護法が施行されてから類例のない水準の切り下げに踏み切らざるを得なかった」として、厚生労働大臣の判断過程の重大な欠落過誤及び裁量権の逸脱濫用を認めるには至らないとしました。
その判断の根底には、生活保護受給者に対する根強い偏見が垣間見えます。これでは司法統制は何ら働いておらず、政治的判断に司法が完全に取り込まれており、生存権(憲法25条)の保障は骨抜きになってしまいます。こうした判断が最高裁で維持されるとは考えられません。
同日の大阪高裁(京都訴訟)と福岡高裁(佐賀訴訟)では明暗が分かれるましたが、これまで言い渡された37判決(地裁29、高裁7)中、原告側は22勝15敗(地裁19勝11敗、高裁3勝4敗)となりました。特に2戦2敗であった大阪高裁で初の勝訴判決が言い渡されたことの意義には大きいものがあります。
現在、最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)にて既に先行訴訟が5つ(大阪、愛知、秋田、兵庫及び福岡の各事件)係属しています。 近く最高裁判決も予想される中、最高裁での勝訴をめざし、全国の原告、弁護団、支援の会の総力を結集して尽力しますので、引き続きご支援をお願い致します。