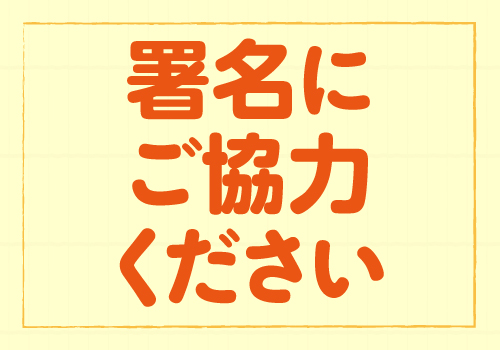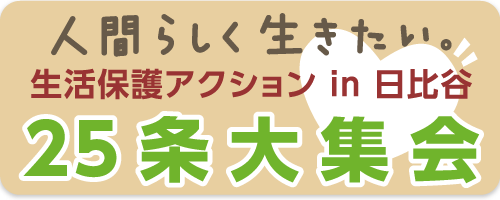ニュース
松山地裁で21例目の勝訴判決が言い渡されました!(判決全文・要旨・弁護団声明などを掲載しています)
2025.3.11

2025年2月28日、松山地方裁判所第1民事部(古市文孝裁判長)は、松山市内在住の生活保護利用者ら30名(提訴時42名)が松山市を被告として提起した裁判で、保護変更処分の取消しを命じる原告勝訴の判決を言い渡しました。
これまで言い渡された地裁判決では30例目で19勝目、高裁判決も含めると21勝目となる勝訴判決でした。(これまでの35判決(地裁30、高裁5)中、原告側は21勝14敗(地裁19勝11敗、高裁2勝3敗)となります。)

当日は、傍聴希望者は70名以上になり抽選が行われました。また、テレビ局、新聞社など多くのマスメディアがつめかけました。原告、弁護団らは、法廷前行進をし、判決に臨みました。裁判長からは判決の主文のみが言い渡され、1分足らずで閉廷しました。あっけないほど短時間でしたが、原告、支援者らは勝ったことを理解すると、法廷内は笑顔であふれました。
本判決は、判断枠組みについて、裁判所が本件改定につき厚生労働大臣の裁量権逸脱・濫用があるか否かを審査するに当たっては、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等の観点から審理判断するのが相当というべきであるとし、老齢加算最判の判断枠組みによることを明確に述べ、最近国側が依拠すべきと主張している朝日訴訟最判については言及さえしませんでした(判決文73~75ページ)。
デフレ調整については、厚生労働大臣の判断過程のうち、①ウエイト参照時点を平成22年とした点、②生活扶助相当CPIの算定に当たり、生活保護世帯の消費構造を反映していない家計調査の結果に基づくウエイトのデータを相当であるとしたことは、一部に論理の飛躍がある等とし、統計等の客観的数値等との合理的関連性や専門的知見の整合性を欠く部分がある。こうした判断過程は、明らかに合理性を欠き、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとしました(判決文88~101ページ)。
本判決の特徴は、このデフレ調整の違法性を導くにあたり、学者意見書を丁寧に検討していることです。被告から出された宇南山意見書についての批判的検討を行い、「平成22年をウエイト参照時点としたのはロウ指数である」とする国の主張と他の統計学者の先生方の意見書との整合性などについて検討している部分(判決文90~92ページ) は、他の地域の判決には余りみられない部分であると思います。
なお、本判決は、ゆがみ調整については、厚生労働大臣の判断過程(2分の1反映の判断過程を含む。)は、いずれも統計等の客観的数値等との合理的関連性や整合性を欠くものとは言えないとし、違法性を認めませんでした。
判決後すぐに、原告記者会見と報告集会が行われました。原告の福岡哲男さんは「国に勝てると考えていなかった。1人だけでは無理だったがみんなの思いがあったから」と話し、一方で10年以上の裁判の半ばで亡くなった原告に触れ「勝利を報告できるのはうれしいがやはり残念」と声を落としました。
80代女性は、市への書類提出時に不正を疑われた経験にふれ「何度も悔しい思いをして涙を流した。甘んじて保護を受けているのではない」と話しました。「冷たすぎる国や自治体とは違い、司法には気持ちが通じた」と感謝し、「これが第一歩だと思う」と決意を新たにしました。
菅陽一弁護団長は「自信はあったが、不安もあった。一言でいえば、ほっとした」と話しました。また、原告側が逆転勝訴した1月の福岡高裁判決をあげ「思い切った判断で良い方向だ」と、上級審に期待していることを話しました。
記者会見の場で、原告3名と弁護団3名にお祝いと慰労の花束が手渡され、会場は大きな拍手に包まれました。
これからも、原告、弁護団、支援する会が一体となって、元気に取り組んでいきます。引き続き、ご支援をよろしくお願いいたします。